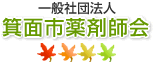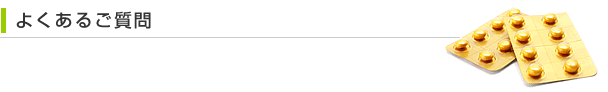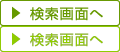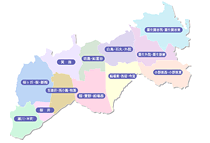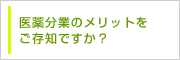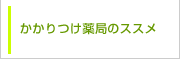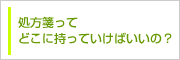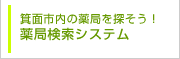薬の飲み方について
- 飲み方の指示で『食間』とは、いつ飲めばよいのですか?
- 「食間」とは食事をしてから約2時間が経過した時間です。食事と食事の間のことになります。
食事中に服用するという意味ではありませんので注意してください。
お薬により服用時は様々です。指示どおり服用することが大切です。
以下によく使われる服用法を記載します。<服用のタイミング>
食 前 食事をする30分前 食 後 食事をした30分後 食 間 食事をした2時間後 食直前 食事をするすぐ前 食直後 食事をしたすぐ後 寝る前 床につく30分前 - お薬を飲み忘れてしまった場合はどうすればよいですか?
- すぐに気づけばそのときに服用してもかまいません。 しかし気づくのが遅く、次の服用時間が近い場合は服用しないほうが良いでしょう。 また、服用を忘れたからといい、2回分を1回で服用することは絶対にしてはいけません。 分からない場合は、薬をもらった薬剤師に聞くのが良いでしょう。
- 調剤薬局で調剤した薬を、市販の薬と一緒に飲んでも大丈夫ですか?
- 服用している薬によりますが、医師、歯科医師を受診してお薬を服用している場合、 市販のお薬の中に同じような効果の成分が入っている場合がありますので、必ず 医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。
薬の保管について
- お薬はどのくらいまで保存しておくことができますか?
- 一般的に市販されているお薬で、しっかり栓をした状態で湿度が低い冷暗所で保存した場合、 製造日から3年間が使用の目安となると思います。 しかし、製造後3年以内であっても、外見、臭いなどに変化がある場合は使用しないほうが良いでしょう。 ただし、医療機関から処方されたお薬はこの限りではありません。 使用期限などを知りたい場合は、お薬を受け取った医療機関で聞くのが良いでしょう。 医療機関から処方された医療用医薬品は原則として、薬を飲む必要がなくなった時点で 廃棄してください。次回発病時には、再度医療機関で診察を受けて、処方された薬を 飲むようにしましよう。
- 薬はどのように保管すればいいですか?
- 高温、日光、湿気を避けて、乳幼児や小児の手の届かない場所に保管 してください。お薬の種類によっては、冷所のものなど、特殊な保管の仕方 の薬もありますので、薬局でよく説明を聞いてください。 間違いを防ぐため、外用薬と内服薬は別々に保管しましょう。
薬の効能・効果・種類などについて
- 自分が飲むお薬にどんな効用があるのか知りたいのですが?
- お渡しするお薬の効用や服用方法など、薬剤師がご説明いたします。 ご不明な点はお気軽におたずねください。 「お薬手帳」をお持ちのかたはご持参くださるようお願いいたします。
- 調剤薬局で処方されたお薬を、市販の風邪薬といっしょに飲んでもかまわないですか?
- 処方されている薬によりますが、同じような効果の成分が入っている場合や 飲み合わせが悪い場合がありますので、同時に内服する場合は医師や薬剤師に相談してください。
- 後発医薬品とはどのようなものですか
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品とも呼ばれています)とは、 先発医薬品(既承認医薬品)の再審査期間(発売後6年以内に有効性、安全性について調査する期間)と 特許期間経過後に「同一の有効成分を含む同一の剤形の製剤で、効能・効果、用法・用量が等しい医薬品」として 承認を得て発売される薬です。 臨床試験などの開発コストもかからないため、低価格で供給することが可能です。
処方箋について
- 処方箋には、有効期限はありますか?
- 原則、処方箋を発行された日を含めて4日間となっています。
5日以上経ちますと、原則としてお薬をお出しできませんのでご注意ください。
有効期限内にお薬をもらいに行けない場合は、処方医に相談することをお勧めします。 - 前回と同じお薬がほしい場合は、直接薬局に行けばもらえますか?
- お薬は、医師の診断に基づき発行される処方箋を元に、その都度、調剤をいたします。
前回のご来店から日数が経っていない場合でも、 処方箋がなければお薬をお渡しすることができません。 お薬を処方してもらった医療機関で再度処方箋を発行して頂ければお薬をお渡しできます。
かかりつけ薬局について
- お薬手帳とはなんですか
- お薬手帳とは、あなたに処方された薬の名前や、飲み方、注意などを記録しておくための手帳です。 この手帳があると、どのような薬をいつ頃から服用しているかがわかります。 常用している薬がある場合、他の医療機関を受診したときにお薬手帳を見せることで、 飲み合わせの問題がない薬を処方してもらえます。 お薬手帳はかかりつけ薬局などですぐに作成してもらえます。
- お薬をもらう前にいろいろ質問されるのはなぜですか?
- 患者様の体質などを記録しておくことで、未然に副作用などからお守りすることができます。 また、住所や電話番号も教えていただくことによりお薬の不備、緊急安全情報などをお伝えすることができます。 しかし、上記のことは個人情報に当たるため、絶対に答えなければならないわけではありません。